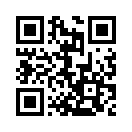2009年02月09日
何故、アメリカのがん患者は減っているのか?
「治療」から「予防」へ。成功への転換点
日本では、死亡率が下がっているがんよりも上昇しているがんの勢いのほうが強く、今後がんの死亡率は上昇の一途をたどるのではないかと予想されています。
ところが、がん患者が増え続けていたアメリカでは1990年を境にがんの罹患率、死亡率ともに減少に転じました。がんによる死亡者は一時は60万人を超えそうだったのが徐々に減少し50万人ぐらいになっています。これはアメリカにおけるがん予防対策、生活習慣改善の取り組みによるところが大きいとされています。
当時アメリカは治療技術に着目し、莫大な予算を投じました。しかし、死亡率は一向に下がる様子をみせず、新たな対策を論議しました。その結果、「治療」ではなく「予防」を重視した対策を進めるべきだという意見に方向転換したのです。この時期のアメリカは国民全体が病気の予防や健康習慣といったことに目覚めた時期でもあり、政府の政策転換は広く社会に受け入れられました。そうした社会背景をベースに、1979年、「ヘルシー・ピープル」という新しい健康対策を打ち出しました。
「ヘルシー・ピープル」1990年のアメリカ国民の健康レベルについて数値目標を設定し、その目標に到達するための疾病予防・健康増進対策を体系化したものです。現在アメリカでは第2次計画である「ヘルシー・ピープル2000」が展開されています。この対策の特徴は数値目標が具体的であるということです。ご参考までに具体的な数値目標をいくつかご紹介します。
・20歳以上の集団で、喫煙率を15%以下へ減少させる。
・「40歳以上の女性のうち、視触診とマンモグラフイ検査を少なくとも過去1回受けたことのある人」の割合を、現状の36% から80%以上にする。
・「50歳以上のうち、この1~2年の間に便潜血を受診した者」の割合を27%から50%以上にする。
これらの目標を達成するため、アメリカ政府は具体的にさまざまな面から支援を行っています。例えば、メディケア(高齢者医療保険)では3つのがん検診を無料で受けられるようにしていますし、民間の医療保険に対しても、加入者に定期的にがん検診を実施するよう指導を行っています。この対策により、がん罹患率、がん死亡率は下がっていきました。
また、特徴的なのは乳がんです。アメリカでもっとも死亡率が減っているがんですが、罹患率は1990年以降、増えもしなければ減りもしない状況です。つまり、乳がんにかかる人は減っていないのに、乳がんで死亡する人はどんどん減っている、これはまさしく検診(マンモグラフィと視触診による)が普及して受診率が上がり、死亡率が下がったということです。
日本では、死亡率が下がっているがんよりも上昇しているがんの勢いのほうが強く、今後がんの死亡率は上昇の一途をたどるのではないかと予想されています。
ところが、がん患者が増え続けていたアメリカでは1990年を境にがんの罹患率、死亡率ともに減少に転じました。がんによる死亡者は一時は60万人を超えそうだったのが徐々に減少し50万人ぐらいになっています。これはアメリカにおけるがん予防対策、生活習慣改善の取り組みによるところが大きいとされています。
当時アメリカは治療技術に着目し、莫大な予算を投じました。しかし、死亡率は一向に下がる様子をみせず、新たな対策を論議しました。その結果、「治療」ではなく「予防」を重視した対策を進めるべきだという意見に方向転換したのです。この時期のアメリカは国民全体が病気の予防や健康習慣といったことに目覚めた時期でもあり、政府の政策転換は広く社会に受け入れられました。そうした社会背景をベースに、1979年、「ヘルシー・ピープル」という新しい健康対策を打ち出しました。
「ヘルシー・ピープル」1990年のアメリカ国民の健康レベルについて数値目標を設定し、その目標に到達するための疾病予防・健康増進対策を体系化したものです。現在アメリカでは第2次計画である「ヘルシー・ピープル2000」が展開されています。この対策の特徴は数値目標が具体的であるということです。ご参考までに具体的な数値目標をいくつかご紹介します。
・20歳以上の集団で、喫煙率を15%以下へ減少させる。
・「40歳以上の女性のうち、視触診とマンモグラフイ検査を少なくとも過去1回受けたことのある人」の割合を、現状の36% から80%以上にする。
・「50歳以上のうち、この1~2年の間に便潜血を受診した者」の割合を27%から50%以上にする。
これらの目標を達成するため、アメリカ政府は具体的にさまざまな面から支援を行っています。例えば、メディケア(高齢者医療保険)では3つのがん検診を無料で受けられるようにしていますし、民間の医療保険に対しても、加入者に定期的にがん検診を実施するよう指導を行っています。この対策により、がん罹患率、がん死亡率は下がっていきました。
また、特徴的なのは乳がんです。アメリカでもっとも死亡率が減っているがんですが、罹患率は1990年以降、増えもしなければ減りもしない状況です。つまり、乳がんにかかる人は減っていないのに、乳がんで死亡する人はどんどん減っている、これはまさしく検診(マンモグラフィと視触診による)が普及して受診率が上がり、死亡率が下がったということです。
Posted by エリック at
11:29
│Comments(0)
2009年02月02日
そもそも、がん免疫治療とは?
こんにちは、半月ぶりですね。もう少しこまめに書きたいんですが
なかなか、時間が取れず申し訳ありません。
前回に引き続き、高度治療法をお伝えします。
「がん免疫療法」について
人間に本来備わっている自然治癒力と最新のバイオテクノロジーを融合させた細胞再生医療です。
現在、がんに対する三大治療法(手術療法、化学療法、放射線療法)は、がん細胞を抑制するとともに正常な臓器や細胞も障害する恐れがあり、強い副作 用によって治療を続けることが困難な患者様が増加しています。近年は、患者様の生活の質(QOL)への関心も高まってきており、QOLを保ちながら行う 『新しいがん治療』が期待されています。
そこで今『免疫細胞療法』が第4番目の治療法として注目されています。
手術療法や化学療法、放射線療法が直接がん細胞を抑えるのに対し、免疫細胞療法は、人間が本来備わっている異物(ウイルス、細菌、がん細胞など)を体内から排除しようとする力(免疫力)を高めて、がん細胞を抑える副作用の少ない治療法です。
最新の病院では、患者様の生活の質(QOL)を保ちながら病状に合わせた免疫細胞療法をオーダーメイドで受けていただけるよう態勢を整えているようです。。
いくらぐらいかかるかと申しますと、下記ぐらいは覚悟しておいてください。
免疫細胞療法の料金表
治療は、自費治療となります。診療や、検査につきましても同様となります。
初診料 : 15,000円
再診料 : 5,000円
(ただし、免疫細胞療法投与日に行う診療費用は、種々の費用に含まれております)
血液検査料 : 15,000円
(全身状態の確認のために必要な項目、腫瘍マーカーなど)
培養初期費用 : 50,000円
(一治療あたり、初回採取時のみ)
培養試薬費用 : 20,000円
(2回目以降、採取時ごと)
※今回は免疫治療の中で代表的な治療を紹介致します。
治療名 : CAT(CD3活性化リンパ球)
特徴 : 末梢血Tリンパ球を培養により活性化させ、増殖させて体内へ戻す。
採取量 : 1回20cc
培養期間 : 約2週間
料金 : 1回21万円 ×6回
なかなか、時間が取れず申し訳ありません。
前回に引き続き、高度治療法をお伝えします。
「がん免疫療法」について
人間に本来備わっている自然治癒力と最新のバイオテクノロジーを融合させた細胞再生医療です。
現在、がんに対する三大治療法(手術療法、化学療法、放射線療法)は、がん細胞を抑制するとともに正常な臓器や細胞も障害する恐れがあり、強い副作 用によって治療を続けることが困難な患者様が増加しています。近年は、患者様の生活の質(QOL)への関心も高まってきており、QOLを保ちながら行う 『新しいがん治療』が期待されています。
そこで今『免疫細胞療法』が第4番目の治療法として注目されています。
手術療法や化学療法、放射線療法が直接がん細胞を抑えるのに対し、免疫細胞療法は、人間が本来備わっている異物(ウイルス、細菌、がん細胞など)を体内から排除しようとする力(免疫力)を高めて、がん細胞を抑える副作用の少ない治療法です。
最新の病院では、患者様の生活の質(QOL)を保ちながら病状に合わせた免疫細胞療法をオーダーメイドで受けていただけるよう態勢を整えているようです。。
いくらぐらいかかるかと申しますと、下記ぐらいは覚悟しておいてください。
免疫細胞療法の料金表
治療は、自費治療となります。診療や、検査につきましても同様となります。
初診料 : 15,000円
再診料 : 5,000円
(ただし、免疫細胞療法投与日に行う診療費用は、種々の費用に含まれております)
血液検査料 : 15,000円
(全身状態の確認のために必要な項目、腫瘍マーカーなど)
培養初期費用 : 50,000円
(一治療あたり、初回採取時のみ)
培養試薬費用 : 20,000円
(2回目以降、採取時ごと)
※今回は免疫治療の中で代表的な治療を紹介致します。
治療名 : CAT(CD3活性化リンパ球)
特徴 : 末梢血Tリンパ球を培養により活性化させ、増殖させて体内へ戻す。
採取量 : 1回20cc
培養期間 : 約2週間
料金 : 1回21万円 ×6回
Posted by エリック at
16:48
│Comments(0)