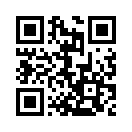2009年04月13日
胃がん検診について
今回は「胃」の検診についてご案内いたします。
2001年の部位別罹患数の統計(男女計)の第1位、 2005年の部位別死亡数の統計(男女計)の第2位「胃」の各検診方法について「国立がんセンター」HPより抜粋。
胃がん検診
(1)胃がん検診の方法
胃の検査方法として一般的なものは、「胃X線検査」、「胃内視鏡検査」、「ペプシノゲン検査」、「ヘリコバクターピロリ抗体検査」です。この中で胃がん検診の方法として、“効果がある”と判定されている検査は、「胃X線検査」です。胃がん検診として、「胃内視鏡検査」、「ペプシノゲン検査」、「ヘリコバクターピロリ抗体検査」は“効果不明”と判定されています。
(2)胃X線検査
胃X線検査は、バリウム(造影剤)と発泡剤(胃を膨らませる薬)を飲み、胃の中の粘膜を観察する検査です。胃がんを見つけることが目的ですが、良性の病気である潰瘍(かいよう)やポリープも発見されます。検査の感度(がんがある人を正しく診断できる精度)は、70~80%です。検査当日は朝食が食べられないなど、検査を受ける際の注意事項があります。副作用としては、検査後の便秘やバリウムの誤飲等があります。
<所感>
多くの部位で発見率が高いといわれるPET検診も腎臓や膀胱の「がん」は見つけることが難しいとも言われており、PET検診とCT検査を複合することによって発見の可能性が高くなるとも聞きましたので、検査を行う際には医療機関に事前に相談し、検査方法を決めることが大事なのではないかと感じました。
いずれにせよ、がんを早期発見には定期的な検診が不可欠かと思います。
2001年の部位別罹患数の統計(男女計)の第1位、 2005年の部位別死亡数の統計(男女計)の第2位「胃」の各検診方法について「国立がんセンター」HPより抜粋。
胃がん検診
(1)胃がん検診の方法
胃の検査方法として一般的なものは、「胃X線検査」、「胃内視鏡検査」、「ペプシノゲン検査」、「ヘリコバクターピロリ抗体検査」です。この中で胃がん検診の方法として、“効果がある”と判定されている検査は、「胃X線検査」です。胃がん検診として、「胃内視鏡検査」、「ペプシノゲン検査」、「ヘリコバクターピロリ抗体検査」は“効果不明”と判定されています。
(2)胃X線検査
胃X線検査は、バリウム(造影剤)と発泡剤(胃を膨らませる薬)を飲み、胃の中の粘膜を観察する検査です。胃がんを見つけることが目的ですが、良性の病気である潰瘍(かいよう)やポリープも発見されます。検査の感度(がんがある人を正しく診断できる精度)は、70~80%です。検査当日は朝食が食べられないなど、検査を受ける際の注意事項があります。副作用としては、検査後の便秘やバリウムの誤飲等があります。
<所感>
多くの部位で発見率が高いといわれるPET検診も腎臓や膀胱の「がん」は見つけることが難しいとも言われており、PET検診とCT検査を複合することによって発見の可能性が高くなるとも聞きましたので、検査を行う際には医療機関に事前に相談し、検査方法を決めることが大事なのではないかと感じました。
いずれにせよ、がんを早期発見には定期的な検診が不可欠かと思います。
Posted by エリック at
16:17
│Comments(0)