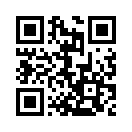2009年03月18日
治療にかかる費用とその支援
今回のテ-マは、「治療にかかる費用とその支援」についてです。
1.高額療養費助成
同じ月の間に、同じ医療施設の同一診療科で保険適用の自己負担額が一定の金額を超えた場合に、超えた額の払い戻しが受けられる制度です。外来と入院とを別にして計算、申請により支給されます。
<支給額の目安(平成18年10月以降)>
課税世帯 : 自己負担限度額= 80,100+{(総医療費-267,000円)×0.01}円
上位所得者世帯: 自己負担限度額=150,000+{(総医療費-500,000円)×0.01}円
2.小児慢性疾患医療費補助制度
小児慢性疾患医療費補助制度とは、18歳未満のお子様で、小児慢性疾患の認定基準に該当する方が、 医療費の助成を受けられる制度です。悪性新生物(がん)と診断された場合、対象となります。
申請先は、お住まいの市区町村の窓口(ほとんどの場合は管轄の保険所)です。
さらに、18歳に達した時点で小児慢性疾患の医療券をお持ちの方のうち、引き続き医療を受ける方は、 20歳未満まで延長することが出来ます(1年ごとに更新)。
3.高額療養費貸付
高額療養費助成は、申請から支給まで2~3ヶ月かかります。それまでの間の医療費支払いのための貸付制度です。無利子ですが、貸付額は実際の医療費支払い額とは異なります。
上記の他にも類似の支援制度がありますが、入院時の食事代、差額ベッド代は、これら高額医療費の対象にはなりません。
自営業などで、国民健康保険に加入されている場合は、社会保険と違って給与保障がありません。生活費として、場合によっては、生活保護を受けることを視野に入れる必要が出てくることもありえます。
大切な家族ががんになったとき、ご本人だけでなく、家族の心にもさまざまな負担がかかります。ご家族 に「治療費が足りないから、充分な治療を受けさせてあげられない」との思いをさせることのないよう、又、安心して治療に専念する為にも「がん」に対する備えの必要性を十分に認識していただきたいと思います。
1.高額療養費助成
同じ月の間に、同じ医療施設の同一診療科で保険適用の自己負担額が一定の金額を超えた場合に、超えた額の払い戻しが受けられる制度です。外来と入院とを別にして計算、申請により支給されます。
<支給額の目安(平成18年10月以降)>
課税世帯 : 自己負担限度額= 80,100+{(総医療費-267,000円)×0.01}円
上位所得者世帯: 自己負担限度額=150,000+{(総医療費-500,000円)×0.01}円
2.小児慢性疾患医療費補助制度
小児慢性疾患医療費補助制度とは、18歳未満のお子様で、小児慢性疾患の認定基準に該当する方が、 医療費の助成を受けられる制度です。悪性新生物(がん)と診断された場合、対象となります。
申請先は、お住まいの市区町村の窓口(ほとんどの場合は管轄の保険所)です。
さらに、18歳に達した時点で小児慢性疾患の医療券をお持ちの方のうち、引き続き医療を受ける方は、 20歳未満まで延長することが出来ます(1年ごとに更新)。
3.高額療養費貸付
高額療養費助成は、申請から支給まで2~3ヶ月かかります。それまでの間の医療費支払いのための貸付制度です。無利子ですが、貸付額は実際の医療費支払い額とは異なります。
上記の他にも類似の支援制度がありますが、入院時の食事代、差額ベッド代は、これら高額医療費の対象にはなりません。
自営業などで、国民健康保険に加入されている場合は、社会保険と違って給与保障がありません。生活費として、場合によっては、生活保護を受けることを視野に入れる必要が出てくることもありえます。
大切な家族ががんになったとき、ご本人だけでなく、家族の心にもさまざまな負担がかかります。ご家族 に「治療費が足りないから、充分な治療を受けさせてあげられない」との思いをさせることのないよう、又、安心して治療に専念する為にも「がん」に対する備えの必要性を十分に認識していただきたいと思います。
Posted by エリック at 12:43│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。